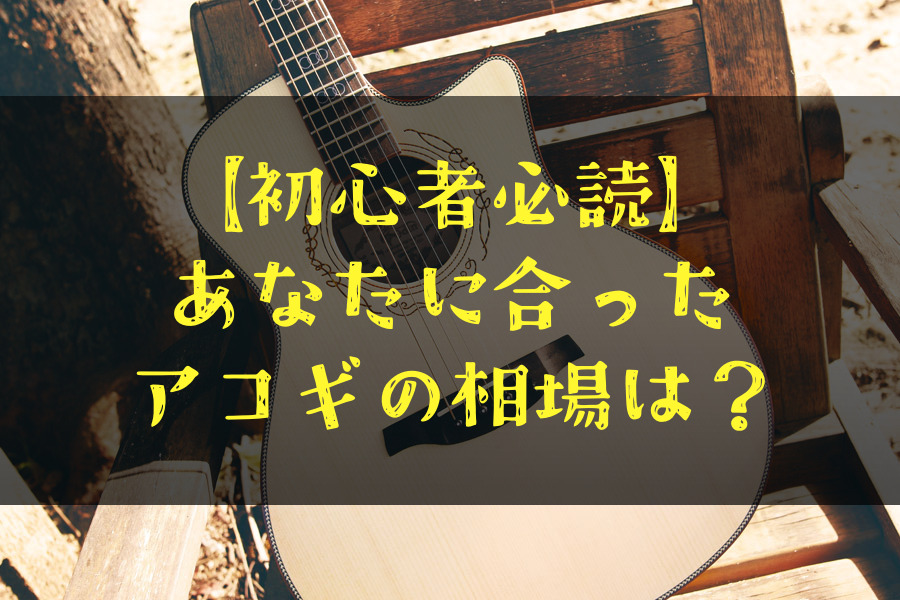みなさんはネットや店頭のプライスカードに書かれた楽器の説明文を見ている時に12Fジョイントとか、13Fジョイントという表記を見たことはありますか?
これはボディとネックが接着しているポジションが何フレット目なのかを表していて、それぞれに強みや弱みがあります。ただ、店頭で見ることの出来る、おそらくほとんどのギターは14Fジョイントなので専門店以外で実際に試すことは難しいでしょう。なので今回の記事ではジョイントフレット毎の特徴を解説していこうと思います。
こんな方におすすめ
- ネックのジョイント位置が違うことで何が変わるのか知りたい
- 小さめでよく鳴るギターを探している
- オールドギターのような雰囲気のギターを探している
アコギのジョイントフレットは3種類
アコースティックギターには大きく分けて3種類のジョイントフレットパターンがあります。それぞれの特徴を踏まえてご紹介します。
14Fジョイント
最もオーソドックスでほとんどのモデルはこの仕様。1932年に発売されたMartin D-28は当初12Fジョイント仕様でしたが、高いポジションまで使用するプレイスタイルと演奏性向上のため1934年に14Fジョイントへ変更。以後、特別なモデルを除いてほとんどのアコースティックギターは14Fジョイントが基本形となっている。
〜 14Fジョイントのメリット&デメリット 〜
| メリット | デメリット |
|---|---|
| カッタウェイがなくてもハイフレットまで演奏が可能 | 12Fジョイントと比べるとやや芯の細い鳴り |
| ネックが細めなので握りやすい | |
| 汎用性が高くオールジャンルで活躍 |
〜 主な機種&おすすめモデル 〜
以下でご紹介するギター以外のほとんどはこの仕様になっているはずです。14Fジョイントのおすすめモデルに関しては価格帯別に解説している下記の記事をどうぞ!
こちらもCHECK
-

【初心者必読】アコースティックギターの相場は?価格帯別にアコギの特徴を解説!
これからギターを始めようとしている方や、自分で買うのが初めての方へ向けたギターの相場事情を解説していきます。 この記事はこんな人におすすめ どんなギターを買えばいいのか知りたい 価格による違いを知りた ...
続きを見る
12Fジョイント
最も歴史が古く、現代のように14Fが主流になるまではこの仕様が当たり前でした。12Fはスケール(弦が張られている長さ)の丁度半分の位置にあり、ナット幅はおよそ45mm〜47mmに設計されていることが多くネックの剛性がしっかりしています。クラシックギターでは今でも12Fジョイントが主流。高い強度から生まれる力強く安定した音色が最大の魅力で、ネックが短くなるのでローポジションの演奏性も最高です。
〜 12Fジョイントのメリット&デメリット 〜
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 小さめのボディでもメリハリのあるパワフルな鳴りを実現できる | ハイポジションでの演奏性は低い |
| ネックが短くなるのでローポジションの演奏性がアップ | |
| ブルースやフォークで人気が高い |
〜 主な機種&おすすめモデル 〜
「パーラーギター」や「ニューヨーカー」といったモデルがこの仕様になっていて、どれも細くて小さなボディが特徴です。Martin D-28Sや1932 D-28 Authenticなど、大型モデルにも12Fジョイントが採用されることがあります。
ニューヨーカーはオーセンティックなルックスも相まって根強いファンが多く、特にフォークソングでよく使われます。
13Fジョイント
2020年頃からリリースされはじめた、14Fジョイントの親しみやすさと12Fジョイントの音質を兼ね備えた新しいフォーマット。まだ商品数は少ないですが、大手ブランドのK.Yairi、Martinも採用していることから高い実用性に期待されています。思い切りストロークしても音が暴れづらく、演奏性も12Fジョイントより向上しています。
〜 13Fジョイントのメリット&デメリット 〜
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 小さめのボディでも芯の太い鳴りが得られる | モデル数が少ない |
| ボディの重量バランスが良い | |
| ネックが補足短いため小柄な方も楽々弾ける |
〜 主な機種&おすすめモデル 〜
K.YairiのTreizeは限定モデルなので、現状安定して供給されているのは下記モデルとなります。もっと沢山の機種がリリースされれば14F一強のアコギ市場ががらっと変わる可能性も秘めています!そこまで高いモデルはないので、弾きやすさと音質の両立を求める方は是非いかがでしょう?好きな人にはバッチリハマると思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?冒頭でもお話したとおり、14Fジョイント以外はなかなか店頭に置いていませんので、少しでもお役に立てればと思い記事にさせていただきました。各仕様の特徴を理解して、あなたの探している条件に合ったギターを探してみましょう!
それでは皆様、引き続き良いアコギライフを!