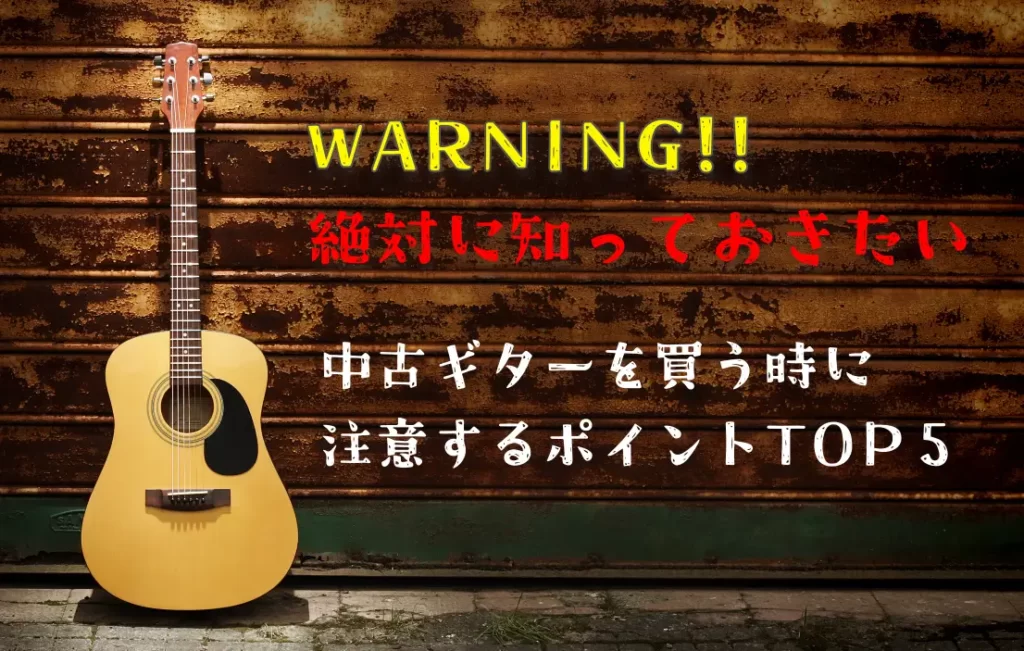

おはようございます、マーリィです!
ギターに親しんでいくほどに、新品以上に多くの魅力を教えてくれる中古品。ヴィンテージとして価値が上がる前に良質なモデルをお得に買いたい!とお考えの方も多いのではないでしょうか。
特に今は楽器屋さん以外にもセカンドストリートやハードオフ等のリサイクルショップにも多く展示されており、ネットを介した取引もヤフオクだけでなくメルカリ、ラクマ等のCtoCコンテンツが増えて選択肢がかなり幅広くなりましたよね。
使わなくなった楽器を手放して次のオーナーがリユースするというサイクルも、良い木材を使用しているギターを次世代に残していくために必要です。
しかし、中古品の状態で注意しなければならない点があるのをご存知ですか?
よく聞く「ネックが反っている」だったり「フレットの残りが○割しかない」なんかは、大掛かりな修理が必要でない限りそんなに大きな問題ではありません。そんなことよりももっと注意深くチェックしなければならないポイントがあります。
今回は中古アコースティックギターを買う時に絶対に注意したいポイント、トップ5をご紹介いたします。
買ってから「失敗した〜・・・!!!」と思わないためにも、是非最後までチェックしてみてください。
投稿者プロフィール

投稿者:マーリィ
京都府出身。楽器店勤務歴13年。
専門学校のリペア講師も務める。
販売員として社内営業成績1位を獲得。
現在は自宅の一室とガレージを使ってギターのリペアおよび製作を行う。
ヴィンテージギターが大好き。
【第5位】ネックの元起き&元折れ
一部の年代のMartinやOvationに見られる症状で、ジョイントフレット(主に14F)を支点にして反っている状態です。
症状
元起きは順反り方向に反っているので弦高が高くなり、とても弾きづらいうえにモデルによっては調整を施したとしても弦高を標準まで下げることは難しいでしょう。
元折れは逆反り方向に反っていて擬似的にネック角度調整された状態で弦高が低いのですが、ジョイント付近のフレットを弾くとビビりや音づまりが発生します。
解決策
簡易的な解決策はこれと言ってありません。症状が軽度な場合はリフレット(約5万円前後)の際に指板を真っ直ぐに整えてやることもできますが、強度が落ちるため音質に影響を与える場合があります。重度の症状だとネック角度を調整する10万超えリペアコースになります。
【第4位】ブリッジの後方が膨らんでいる
古いギターや十分な強度設計がされずに作られたギターに見られる症状で、ボディトップが弦の張力に負けて変形している状態です。ブリッジ後方が膨らみ、ブリッジの前方は逆に陥没するように凹んでしまっています。
症状
後述の”ブリッジの頂点が高くなっている状態”になりやすく、さらにクラックやブレイシングの剥がれに繋がる場合もあるので要注意。
The Best of Flat topと呼ばれたオリジナルのGibson Advanced Jumboの現存数が少ない理由は25.5 inchのロングスケールによる強い弦の張力に加えトップが非常に薄かったからとされています。オリジナルの実物を触ったことがありますが、トップ板の暑さが2mm前後で怖くなるぐらいペラペラでした。
解決策
ある程度時間が経っているギターであれば木が安定していますのでそれ以上動く可能性は低いです。しかし10年以内に作られたギターでこの症状が出ている場合はまだ大きく動く可能性が高いので、しばらくチューニングを落として湿度調整された部屋に安置して様子を見ましょう。それで治らない場合はブレイシングに手を入れて補強しないといけない事もあるので一度リペアマンに見てもらいましょう。それなりの費用は覚悟しておかなければなりません。
【第3位】弦の巻き返しがサドルに乗っている
ノーメンテナンスでヘビーユースされた古いギターにみられる症状で、サドルの上に弦のボールエンドから始まっている巻き返し部分が乗ってしまっている状態です。
意外と多くのオールドギターがこの状態に陥っており、よく見ないと気づきにくいので注意が必要です。
症状
弦長が変わってしまい音程が合わずこもった抜けの悪いトーンになってしまいます。弦高の高いギターはブリッジを削ってサドルを低くする場合がありますが、その際にブリッジ裏側にあるブリッジプレートまでケアしていないとこうなってしまいます。
また、ボールエンドによってブリッジプレートが削れていくことでもこの状態になってしまうことがあります。
解決策
最も簡単にこの状態を脱する方法は新しい弦を張る時に古い弦のボールエンドを取り出し、新しい弦に通すことで弦の巻き返し部分を短くしてやる事ですが、ブリッジプレートに埋め木等をして補強するのがおすすめの修理方法です。専用の工具が必要なためリペアマンに依頼することを推奨します。
【第2位】ブリッジの頂点が高い位置にある
YAMAHAの古いFGやジャパニーズヴィンテージ(オールド)と呼ばれる設計が古いギターや、中古に限らず安価なギターにみられる症状で、指板の高さよりもブリッジの高さの方が明らかに高い状態です。
症状
ヘッド側から指板とブリッジを水平に見てブリッジの頂点のほうが高い場合、必然的に弦高は高くなります。実際に店頭で見ることは簡単ですがネット2掲載されている写真では非常に分かりづらい…というかほぼ分からないので注意です。
解決策
標準以下の弾きやすい弦高にするにはネック角度を変更するかブリッジを削る必要があります。多くの場合、さらにブリッジプレートにテコ入れして強度を補ってあげる必要がありますので修理費はかさみます。
【第1位】接着剤が劣化している
古いギターや管理の行き届かなかったギターあるいは安価なモデルの中古品にみられる症状で、ブリッジやブレイシングが浮いている場合はとても危険なためすぐに修理が必要です。特にブレイシングが外れている場合は外見で分からないので、必ずタッピングして確認する必要があります。
症状
ブリッジやブレイシングが剥がれているのを知らずにそのまま使い続けると後に大きなしっぺ返しを食らってしまう要注意項目です。最悪演奏中にブリッジが突然剥がれてギターも弾き手も大怪我をしてしまいかねません。
解決策
専門のリペアマンにチェックおよび修理してもらうのが最もおすすめです。修理するには専用のクランプが必要になるため、自分で治すにしても修理費はかさんでしまうでしょう。
中古品を買う前に必ずチェックしましょう!
本日ご紹介したチェックポイントはどれも重要です。抜けがあると修理するのに余計なお金がかかってしまったり、最悪の場合、思わぬ怪我をしてしまうこともありますのでもれなく確認するようにしましょうね!
それでは皆さん、引き続き良いアコギライフを!